こんにちは、あーさんです。
現在3歳半を過ぎた長女が、「発達障害(自閉症スペクトラム)」と診断されたので、疑いを持ち始めてから、実際に診断されるまでの長い道のりを、記録としてここに残しておきます!
目次
長女が自閉症スペクトラムと診断されるまで
夫が発達障害疑惑濃厚ということもあり、私は長女が1歳半健診の時には既に、

「この子は発達障害かもしれないぞ…?」
と疑いを持ち始めていて、しかしその時に相談した心理相談員さんは、
「そう(発達障害)は思えない」
と言われていました。
(参考までに! 1歳半健診の時のお話は、こちらから)

が、やはり私の疑問・不安はまっさらに晴れず、長女が成長にするにつれ、
「やっぱりこの子は発達障害かもしれない…」
と思い続けていました。
その一番の理由が、
長女の言葉の遅れでした。
1. 常に長女に疑いを持っていた2歳以降
こちらの記事に長女の症状を書きましたが、

我が家の長女の場合、とにかく言葉が遅いのが一番わかりやすい症状でした。
2歳を過ぎてから「わんわん」等ひとつの単語が出て来始めて、満3歳を過ぎてようやく二語文程度、しかし会話が成り立たない。

長男も言葉は遅い方でしたが、3歳前後には大人と意思疎通ができるくらい会話はできていたし、同じクラスのお友達なんて長女より誕生日が遅い子でも普通にお喋りしていたので、言葉が遅いことは誰が見ても明らかでした。
それでもすぐに相談に行かなかったのは、
- 通常の心理相談員の方に相談しても、再度「問題無し」と言われる恐れがあったため
- 私の住む自治体では、段階を踏まないと専門の病院に紹介状を書いて頂けないこと
ということが挙げられます。
要は、言葉の遅れは明らかでも、「個人差」とかで無問題にされるのを避けたかったのです(笑)
3歳児健診で医者に「言葉の遅れ」を指摘されれば、相談員の方も無下に「個人差」で片付けないだろうと思ったわけです。
なので、まずは3歳児健診で一応規定の心理相談をして、そこで何がなんでも専門の病院への紹介状を書いて頂こうと決めていたのです。
2. 3歳児健診で満を持して「言葉の遅れ」を指摘される
待ちに待った(?)3歳児健診では、月齢が似たり寄ったりの子よりも長女が明らかに喋れていないのを再確認。

健診時、人見知りが激しく、慣れない場所でいきなりパンツ一丁にされた長女は、終始パニックでした。
更に、お医者さんからの、
「うーん、喋れないかぁ」
という一言に、ズン…と無駄に気落ちしながらも、母子手帳にはっきり「言葉の遅れ」が書かれたことを確認し、意気揚々と心理相談に予約。

「紹介状書いてください!!」
そしていざ心理相談が始まり、私はすぐに、
- 夫が発達障害の疑惑が濃厚
- 長女の言葉がとにかく遅く、医者にも指摘されたこと
を伝えた上で、「専門の病院に行ってみたいので、紹介状を書いて頂きたい」と真っ向勝負を仕掛けました。

「おにゃしゃす!!」
すると、心理相談員の方は、

アッサリ!!
「ただ、私は紹介状を書けないので、一度、発達障害専門の心理相談に来て頂いてもよろしいですか?」
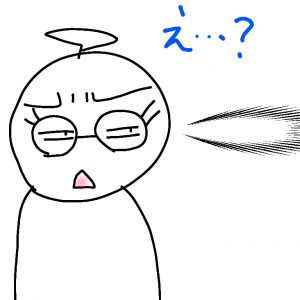
「そんなのあったの…?」
自治体のホームページには「発達相談」としか書かれていなかったので、心理相談員が相手の相談かと思っていたら、なんと専門の医師による相談だったようです。
早く言ってよ~。←完全に自分の調査不足。
とりあえず発達障害専門の心理相談とやらに予約をし、その日の3歳児健診は終了しました。
3. 発達障害専門の心理相談で「発達の遅れ」を指摘される
専門の医師が月一で相談を受けている「発達障害」専門の相談で、いつもの夫の話や長女の言葉の遅れの話をすると、相談員の方は長女にいくつか質問しました。

「何歳かな?」
「おへそはどこかな?」
「スプーンはどれかな?」
対する長女!

「……あんさい(3歳)」
「……」
「……」

「(人見知りしてるから普段より全然喋れてねぇ~!!)」
結果、
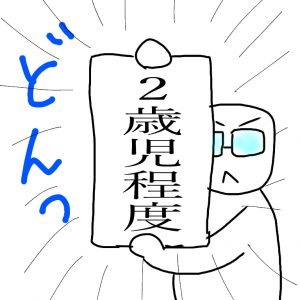
「2歳児程度の発達です」
やっぱりね!!
予感はしていましたが、案の定でした。
満3歳にして、1年遅れの発達具合だったようです。
はっきりと言葉にされるとやはりショックでしたが、それでも紹介状を書いて頂き、当時は

「ようやくここまで来た…」
と、安心した覚えがあります。
4. 専門の病院に行ってみる
ADHDの甥っ子も通院している近隣の専門病院に予約が取れたのは、それから3ヶ月後のことです。
最初は夫にも仕事を休んで貰い、夫婦と長女の3人で病院に行きました。
事前に病院から郵送されてきた問診票も持参して、いざ先生と面談です。

最初の面談では、長女の言葉の遅れを一番に説明。
先生は遊んでいる長女の風景や、問診票、私の話を聞いて、
「その(発達障害の)気はあるけど、言葉は小学校入学までには追い付いてると思うよ。でも、一応検査はしようね」
ということで、他にも、私たち親の接し方・遊び方も説明してくれて、初診は終わりました。
5. いざ、発達検査
1ヶ月後、発達検査のためにもう一度病院へ。
KIDS(乳幼児発達スケール)TYPE T
という、親が子どものできること・できないことを項目別にチェックしていく検査方法らしく、私がこちらを記入している間、専門の鑑定士?さんが長女の側について何やら発達検査をしてくれました。
「積み木を同じように積んでみようねー」
とか、
「同じ絵はどれかなー」
とか、何やら優しく色々と遊んでくれていて(実際は検査ですが)、人見知りが激しい長女も、すぐに慣れていました。
最後に、口頭で

と、いくつか私に直接質問もあり、結局検査自体は1時間くらいでした。
6. 自閉症スペクトラムと診断される
発達検査から更に1ヶ月後、検査結果報告を聞くために再び病院へ。
その時に、正式に自閉症スペクトラムと診断されました。
前回の検査結果を聞くと、親が記入するKIDSの総合発達指数が68点。
長女は当時3歳4ヶ月でしたが、2歳3ヶ月程度の発達だということでした。
1年以上、発達が遅れていたわけです。
それと、専門の方が行っていた遊びを見ながらや、親との質問形式での発達検査でも同じく68点だったそうです。
主治医の先生曰く、親の自己申告であるKIDSと専門家が検査する点数が一致するのは、極めて稀らしいです。

よくわからんがえっへん(笑)
夫が発達障害濃厚なので、普段から長女をよく観察していた甲斐があったということでしょうか?
なんにせよ、3歳半でようやく発達障害が確定しました。
私はどこかで確信していたのでさほどショックではなく、逆に安心したくらいですが、長女の検査結果を報告した時はなぜか夫の方が、

「マジかよ…」
と驚いていて、夫の反応の方に私は驚いていました(笑)
(漠然とそうだろうなとは感じてはいたけど、改めて宣告されるとショックだったらしいです。今は開き直って、あれこれ長女の今後を考えています)
まとめ
1歳半健診時の相談で「問題無し」と言われてからも言葉の遅れが顕著で、常に、
「この子は発達障害かもしれない」
と長女を疑っていましたが、3歳児健診をきっかけに動き出した、長女の発達障害確定までの道のりでした。
ちなみに、3歳児健診から発達障害の診断までは、約半年かかりました。
現在は、定期的に病院に行って長女の様子を報告しながら、先生と面談しています。
病院の予約やら検査結果までなんだかんだ時間がかかるので、もし自分のお子さんの発達で心配なことがあれば、紹介状を書いて貰うためにも、まずは自治体に相談にするのが早いかもしれませんね。
…というわけで、3歳長女の発達障害が確定。相談してから診断・確定するまでの長い道のりを残します でした!
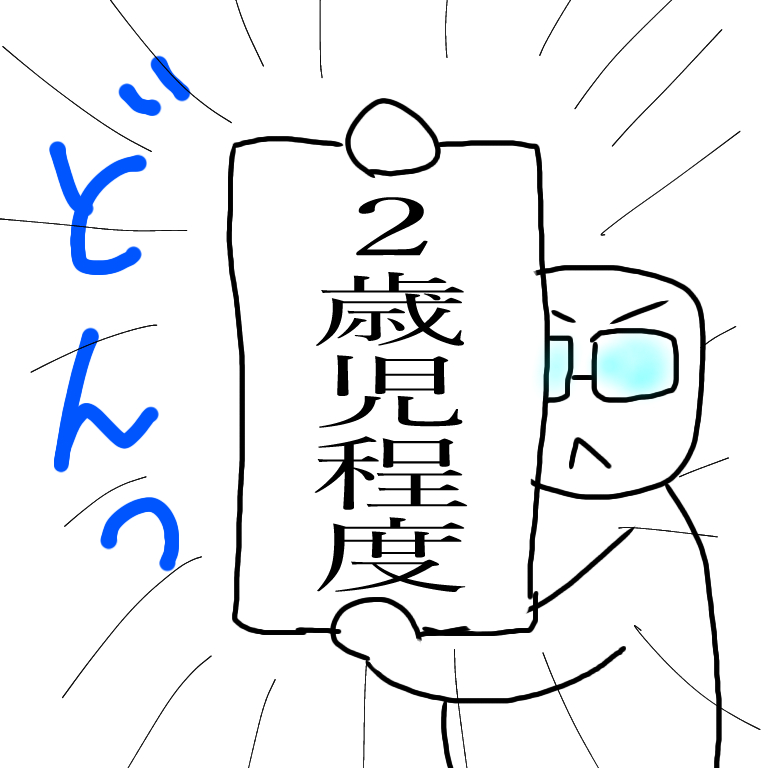


コメント